葬儀後に行う四十九日(しじゅうくにち)法要は、故人や遺族にとって大切な行事のため、事前にしっかりと準備をしておく必要があります。
しかし、そもそも四十九日とはどのような意味があり、なぜ法事・法要をしなければならないのか、日程はいつにすればよいのか、よく分からない方もいらっしゃるでしょう。
そこで、四十九日法要について、知っておきたい基礎知識や法事の流れ、準備しておくべき項目をポイントごとに分かりやすく解説します。
気をつけたい注意点や、お布施の金額・包み方・服装、四十九日法要に関するよくある質問までまとめてご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
目次
四十九日とは?

四十九日とはどのようなことをいうのか、言葉の意味や、四十九日法要の役割や必要性について詳しく解説します。
四十九日の意味とは?
四十九日とは、故人が亡くなった当日を1日目として、49日目にあたる日のことであり、仏教ではこの日に四十九日法要を営むのが一般的です。
| 宗教 | 葬儀後の儀式 |
| 仏教 | 四十九日法要 |
| 神道 | 五十日祭 |
| キリスト教 | 召天記念日/追悼ミサ |
仏教以外でも、神道では五十日祭、キリスト教では召天記念日や追悼ミサなど、四十九日法要と同様に、葬儀後に儀式を行うのが一般的です。
具体的に故人の四十九日がいつなのか、今すぐ知りたい方は以下のサイトで亡くなった日を入力すると、日程を自動的に計算して調べられます。
四十九日法要をする理由と役割とは?
四十九日法要をするには理由があり、故人と遺族のためになる3つの役割があるため、ポイントを押さえて解説します。
- 故人を偲んで供養する
- 遺族が忌明けを迎えて日常を取り戻す
- 死への悲しみに区切りをつける
故人を偲んで供養する
人が亡くなると、しばらくのあいだは「あの世」に行く準備の期間を過ごすと考えられてきました。仏教ではその期間を四十九日間とし、この間に次の行き先が決まると言われています。
昔からの言い伝えでは、亡くなって 7日目(初七日) に「三途の川」を渡るとされ、生前の行いによって渡り方が変わると考えられています。そして 35日目(五七日) には「閻魔さま」が登場し、故人の行き先を大きく左右する裁きを行うとされてきました。
その後、49日目(七七日) に最終的な行き先が定まるとされ、この日を区切りに遺族は「四十九日法要」を営みます。とくに四十九日は、故人が無事に成仏できるよう願う大切な日とされ、親族や親しい人が集まって供養を行います。
本来は亡くなった日から七日ごとに法要を重ねて祈るのが習わしでしたが、近年では初七日の法要を葬儀の日に合わせて行い、その後は四十九日まで省略することが多くなっています。
このように、四十九日法要は「仏教的には故人の行き先が決まる大切な日」であり、「民間信仰では閻魔さまの裁きを経て迎える区切りの日」として受け継がれてきたのです。
遺族が忌明けを迎えて日常を取り戻す
四十九日法要を終えると忌明けを迎え、遺族は日常を取り戻して、以前と変わらぬ生活を送ります。
故人が亡くなってから四十九日までの忌中の期間、仏教では故人の魂が成仏するように、遺族は故人の冥福を祈り、喪に服して慎ましく過ごすのが基本マナーです。
仏教では故人の供養をすることが自ら徳を積む善行に相当すると考えられており、法要は追善供養とも呼ばれ、四十九日法要を終えると、一周忌・三回忌と続きます。
ただし、浄土真宗では死後すぐに極楽浄土へ行けると考えられており、四十九日法要は仏教の教えに触れる儀式と考えられているため、宗派による違いがあることを知っておきましょう。
死への悲しみに区切りをつける
四十九日法要を終えると遺族にとって一区切りとなるため、忌明けは故人の死に対する悲しみに区切りをつけ、前向きな気持ちで歩んでゆく機会となります。
葬儀後は、故人に関する死後の手続きや四十九日法要の準備などで慌ただしい日々が続くため、四十九日を過ぎてから急に寂しさがこみ上げてくる方もいらっしゃるでしょう。
大切な人を失うと、どうしようもない悲しみや苦しみを感じることがあり、心身の不調からグリーフケアが必要になる方もいらっしゃいます。
不安な方は、ぜひ以下の記事をご覧いただき、知識や対処法の習得にお役立てください。
参考:死別による辛い悲しみを克服する6つの方法!喪失感やストレス解消法
四十九日の法事・法要の必要性
日本では仏教への信仰心というよりも、古くから伝統やしきたりを大切にする風習として、法事・法要をするご家庭が多い傾向にあります。
実際、結婚式ではキリスト教式が多い反面、お葬式では葬儀形式のうち仏式が全体の約9割を占めると言われており、弔い方や供養のスタイルは地域によって特色があるのが実態です。
なお、法事とは法要に列席してくれた方々に対して、感謝の気持ちを込めて振る舞う「お斎(おとき)」の会食を含めた一連の行事のことをいいます。
四十九日法要や一周忌・三回忌では、家族のみならず親族などを招き、法要後におもてなしとして食事の席を用意するのが一般的です。
法事・法要をしないと、親族や近親者とトラブルになる可能性があるため、四十九日で法事・法要をするかどうか迷う場合は、故人の血縁者や親族に相談してみましょう。
四十九日法要の日程の決め方

四十九日法要の日程を決める際には、押さえておきたい2つのポイントがあるため、手順を踏まえて解説します。
- 四十九日法要は亡くなってから49日目に近く、親族が集まりやすい日程を選ぶ。
- 菩提寺に、四十九日法要が可能な日程を確認する。
四十九日法要は亡くなってから49日目に近くて親族が集まりやすい日程を選ぶ
四十九日法要は、亡くなってからちょうど49日目に執り行うのが理想ですが、当日が難しい場合は、四十九日に近い日程を前倒しして選びましょう。
一般的には、遠方にお住まいの親戚などにも配慮して、参列者が集まりやすい土曜日・日曜日・祝日など、四十九日に近い休日を選択します。
菩提寺に四十九日法要の日程を確認する
四十九日法要の日程は、必ず事前にお付き合いしている菩提寺のスケジュールを確認して決定してください。
寺院ではお盆や、春と秋のお彼岸が繁忙期となるほか、お寺としての行事などもあるため、法要の日程は早めに相談しておきましょう。
四十九日法要の流れとタイムスケジュール

一般的な四十九日法要の流れについて解説しますが、法要の内容や各所の位置関係などによって流れや所要時間は異なりますので、あらかじめ菩提寺や依頼する葬儀社にご相談ください。
| 順序 | 時間 | 内容 |
| ① | 10:00 | お仏壇の開眼法要 |
| ② | 11:00 | 四十九日法要 |
| ③ | 12:30 | 会食 |
| ④ | 14:30 | お墓の開眼法要・納骨式 |
| ⑤ | 15:00 | 解散 |
①お仏壇の開眼法要
お仏壇を購入して初めて使用する場合は、自宅へ僧侶を招き、仏像や掛軸などとともに、ご本尊の開眼法要をしてもらう必要があります。
時間的に難しい場合は別日に行うケースもあり、すでに利用しているお仏壇がある場合には開眼法要は不要です。
②四十九日法要
法要をする場所へ移動して、親族などの参列者が揃ったら、お位牌の開眼法要と魂の入れ替えを含めて四十九日法要を営む流れです。
僧侶の支度ができたら声をかけて、「本日は宜しくお願いします」とお布施を渡して挨拶をします。読経供養にかかる時間は、おおよそ1時間程度が目安です。
③会食
四十九日法要の後に食事をする際は、僧侶や参列者へ簡単なお礼の挨拶をしてから会食場所へ誘導し、料理を振る舞います。
納骨する場所で四十九日法要をする際は、納骨後に会食をした方がスムーズな場合もあるため、予約時間などを調整して臨機応変に対応しましょう。
④お墓の開眼法要と納骨式
お墓へ移動して、墓前で読経による開眼法要や納骨式を行って遺骨の埋葬や納骨を行います。
納骨方法やお参りの方法は納骨先によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
⑤解散
一連の儀式が終わったら、僧侶にお礼の挨拶をして、喪主は参列者に対して次のような挨拶の言葉を伝えます。最後に引き物を手渡して個別にお礼を伝えましょう。
「本日は長い時間、お付き合いいただきありがとうございました。お陰様で無事に四十九日を済ませることができ、皆さまに見守られて故人も喜んでいると思います。今後とも変わらぬお付き合いをどうぞ宜しくお願い申し上げます。」
四十九日法要で準備するべき7つのこと

四十九日法要で事前に準備するべき7つの事項について、具体的な手順を解説しますが、準備に時間のかかることもあるため、葬儀後は早めに準備を開始しましょう。
- お香典返しと引き物の準備
- 本位牌とお仏壇の準備
- お墓と納骨の準備
- 四十九日法要の場所と食事の予約
- お布施の準備
- 服装と身だしなみの準備
- 持ち物の準備
①お香典返しと引き物の準備
遺族は参列者に対してお礼の品物を用意するのがマナーであり、葬儀ではお香典への返礼品としてお香典返しを、法要では引き物をそれぞれ準備します。
近年は葬儀の当日にお香典返しをするケースが多い一方で、香典金額やお返し物の相場は地域によって異なり、関東などでは香典の1/3〜1/2程度の品物を贈るのがマナーです。
その他の地域でも、高額な香典をいただいた方には「後返し」として、四十九日法要が終わるタイミングで香典返しが届くように、挨拶状を添えて贈るケースが多い傾向にあります。
また、葬儀で弔電や供花、供物をいただいた場合や、生前にお見舞いをいただいた場合は、四十九日法要が終わるタイミングで届くように、手紙やはがきでお礼を伝えましょう。
四十九日法要の引き物では、3,000〜5,000円程度の金額の品物を用意して参列者へ渡すのが一般的です。
水引は黒白の結び切りを使用し、表書きは「志」とするのが一般的ですが、地域によっては黄白の結び切りの水引を使用する場合や表書きを「満中陰志」「粗供養」とします。
②本位牌とお仏壇の準備
四十九日法要では、葬儀で使用した白木の仮位牌から本位牌へと故人の魂を入れ替える儀式を行うため、あらかじめ本位牌を購入しておきます。
お位牌は仏壇店で1万円程度から市販されており、お仏壇に合わせて、イメージや材質、サイズなどを選び、戒名や生前の俗名、年齢、亡くなった没年月日などの彫刻が必要です。
彫刻には1〜2週間程度かかるため、お仏壇ともども四十九日法要に間に合うように事前に自宅へ安置して準備しましょう。
なお、浄土真宗では本位牌の代わりに過去帳を用意するのが一般的ですので、仏壇店にご相談ください。
③お墓や納骨の準備
故人の納骨先が決まっている場合、四十九日法要の日に納骨するのが一般的ですので、霊園や墓地、納骨堂や寺院などのお墓の管理者に事前に連絡しておきましょう。
石材店による墓石への彫刻や、草むしりや掃除など、事前準備が必要な場合もあるため、お墓については早めに必要事項を確認して用意します。
なお、お墓がなく四十九日法要に間に合わない場合は、準備ができるまで自宅で遺骨を供養して、納骨先が決まってから納骨式をすれば問題ありません。
近年は、霊園や寺院が遺骨の管理や供養を行う永代供養が人気を集めています。永代供養墓にはさまざまな種類があるため、以下の記事を参考になさってください。
参考:永代供養墓は6種類!特徴や費用の比較と選び方のポイントをまとめて解説
④四十九日法要の場所と食事の予約
四十九日法要は、自宅や斎場、お寺や霊園の法要施設、ホテルなど、さまざまな場所で行うことができます。日程が決まったら希望する会場に問い合わせて、僧侶や参列者の人数分の食事を予約しましょう。
法要施設の利用料や備品の使用料、人件費は場所によって異なりますが、一般的には3〜5万円が相場です。
食事は仕出し料理やお弁当、飲食店やホテルでの飲食代など、1名あたり3,000〜1万円が相場です。
法要では、仏花や果物、お菓子などの供物が必要となるため、当日の持ち物についても確認しておきましょう。
⑤お布施の準備
四十九日法要では、次の3つをそれぞれ白無地の封筒に入れ、黒墨で表書きを書いて包みます。
- 御布施:3〜5万円程度(開眼法要や納骨式を一緒に営む場合:5~10万円程度)
- 御車代:5,000~1万円程度
- 御膳料:5,000~1万円程度(食事をしない場合)
お布施の金額は、地域や菩提寺などによって異なります。
直接お寺に尋ねても失礼にはあたりませんので、気になる場合は「皆さま、どのくらい包まれていますか?」などと確認しておきましょう。
そのほか、納骨先や宗派によって、納骨手数料や卒塔婆代(3,000円程度)などが必要となるため、納骨先や菩提寺へご確認ください。
⑥服装と身だしなみの準備
四十九日法要での服装は、遺族も参列者も喪服が最適であり、三回忌までは葬儀と同じく「準喪服」と呼ばれる漆黒の喪服を着用するのが一般的です。
男性は白いワイシャツと黒いネクタイ・ベルト・靴、女性は肌の露出を抑えたアンサンブルスーツやワンピーススーツと黒いストッキングと靴を合わせます。
子どもは学生服やモノトーン系の私服で問題ありませんので、目立つ色柄を避けて、清潔感のある洋服や靴を選びましょう。
四十九日法要も葬儀と同様の身だしなみが求められます。髪型やメイクは華美にならないよう質素さを意識し、マナー違反にならないよう注意しましょう。
⑦持ち物の準備
四十九日の持ち物リストをご紹介しますので、忘れ物のないよう事前にチェックしてご用意ください。
- 白木位牌:風呂敷で包みます
- 本位牌:購入時の箱に入れたままでも問題ありません
- 遺骨:風呂敷や布で包むか丈夫で安定したボストンバッグなどへ入れて持ち歩きます
- 遺影写真:持参する場合は風呂敷等で包みます
- 仏花・供物:必要な場合は持参します
- 引き物:持ち帰り用の紙袋も用意します
- お布施:袱紗に入れて持ち歩きます
- 数珠:1人1つずつ自分用の数珠を持参します
- ハンカチ:白や黒の無地のハンカチ
- フォーマルバッグ:男性は手ぶらで構いません
四十九日法要で気をつけるべき2つの注意点

四十九日法要では、気をつけるべき2つの注意点があるため、ポイントを押さえて解説します。
- 四十九日法要や会食の会場選びに注意する
- 四十九日法要や納骨式を依頼する寺院に注意する
四十九日法要や会食の会場選びに注意する
四十九日法要の際は、納骨や会食についても考慮し、スムーズに行える場所を選びましょう。参列者の移動手段や駐車場の確保にも注意しましょう。
特に自分で懐石料理店や料亭などの飲食店を予約する場合は、予約時間に注意が必要です。法要の時間が予測しにくいことも多いため、ご注意ください。
四十九日法要や納骨式を依頼する寺院に注意する
納骨先によっては、読経供養できる寺院が経営主体に限定される場合があり、葬儀や四十九日法要を依頼した僧侶が納骨式を行えないケースもあるため注意が必要です。
地域の公営墓地への納骨や、納骨先のお寺が四十九日法要を行う場合なら問題ありませんが、不安な場合はあらかじめ納骨先に確認しておきましょう。
四十九日法要の準備でよくある質問
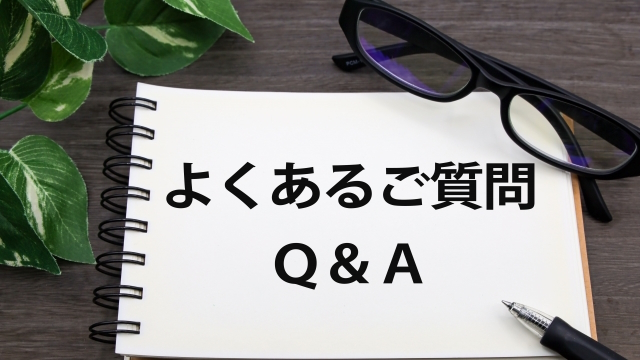
四十九日法要でよくある質問をご紹介しますので、気になる項目があれば、疑問やお悩みの解消にお役立てください。
四十九日法要の参列者はどこまで呼ぶの?
四十九日法要で誰を招くべきかといえば特に決まりはなく、遺族や故人の親族が話し合って決めれば問題ありません。
身内だけでやる場合もあれば、故人の親しい友人・知人に声掛けして盛大に行う場合もあるため、遺族や親族が納得のできる四十九日法要にしましょう。
たとえば、祖父母の四十九日法要に、血縁者の配偶者が参列しないケースもありますので、自分が参列すべきか迷う場合は、トラブルにならないよう事前に遺族に相談してください。
四十九日法要に参列する際のお香典はいくら包めばいい?
四十九日法要に参列する遺族や故人の友人・知人などは、お香典を包んで渡すのがマナーで、香典金額は故人との関係によって、一般的に次のとおりです。
| 故人との関係 | 金額 |
| 両親 | 1〜5万円 |
| 祖父母 | 1〜3万円 |
| 兄弟姉妹 | 1~5万円 |
| 親戚 | 5,000円~3万円 |
| 一般参列者 | 3,000円~1万円 |
香典の相場は地域によっても異なりますが、遺族に負担をかけないよう、会食をする場合はその分の金額も加算するようにしましょう。
- 表書き:御仏前・御佛前・御香料・御供物料
- 水引:印刷(5,000円以下)・白黒(1万円以上)・双銀(5万円以上)
香典袋は「御仏前(御佛前)」の表書きが一般的で、仏式なら無地のほか、蓮や雲海の絵柄付きなどのタイプが市販されています。
四十九日法要の日にやるべきことは?
故人の相続人が揃いやすい四十九日法要の日は、形見分けを行ったり、遺産相続の話し合いをしたりするご家庭が多くあります。
あらかじめ、相続人同士で声をかけ合って遺品整理を進め、四十九日法要後に話し合いがしやすいように準備しておくとスムーズです。
ただし、これらは親族トラブルになりやすいうえ、故人の遺言書がない場合は相続法に基づき、法定相続人全員の意向に基づいて進めなければならないため注意しましょう。
出典:知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】(政府広報オンライン)
まとめ:四十九日法要では事前に7つの準備をしましょう

四十九日法要について、意味や流れと、準備方法の手順や注意点を解説しましたが、まとめると次のとおりです。
- 四十九日は故人があの世にたどり着く重要な行事で、葬儀後の初めての法要となる四十九日法要は遺族や参列者にとっても大切な意義があり、法要後は会食をするのが一般的。
- 四十九日法要の流れは、前後にお仏壇やお墓の開眼供養や納骨式をともなう場合もあり、四十九日法要のみなら1時間程度だが、法事として会食まで含めると、最大5時間程度かかる場合もある。
- 四十九日法要では、次の7つの準備が必要となる。①お香典返しと引き物 ②本位牌とお仏壇 ③お墓と納骨 ④四十九日法要の場所と食事の予約 ⑤お布施の準備 ⑥服装と身だしなみ ⑦持ち物
四十九日法要は、故人や遺族・親族にとってとても大切な日であるとともに、喪主や遺族は事前準備が多くあり、うっかりミスやトラブルが起こりやすいため注意が必要です。
北のお葬式では北海道一円の葬儀を承っており、葬儀後に必要な四十九日法要についても事前準備から当日の対応まで、すべてお任せいただけます。
会場や料理の準備と配膳や接客、僧侶手配、お仏壇や本位牌やお墓のほか、遺品整理や不用品の処分、遺産相続についてもご相談可能ですので、どうぞお気軽にお問い合せください。






