形見分けでは、渡す側と受け取る側の双方に大切なマナーがあり、適切な時期や最適な品物、スムーズに進めるための手順があります。
さらに、形見分けは親族間のトラブルにつながりやすく、相続税の対象となる場合もあります。法律に違反した場合は10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金が科せられることもあるため、十分に注意しましょう。
そこで、形見分けについて、知っておきたい基礎知識から気をつけるべき注意点まで、ポイントを押さえて徹底的に解説します。
形見分けでよくある質問についてもご紹介しますので、トラブルやマナー違反を防いで、故人の大切な遺品の形見分けにお役立てください。
目次
形見分けとは?意味や必要性を理解しよう

形見とはどのようなことをいい、なぜ形見分けをするのか、意味や必要性について基礎知識を解説します。
形見分けの意味とは?
形見とは、亡くなった故人や別れた人が残した品物、もしくは本人からもらった品物のことをいいます。
これに対して形見分けとは、家族や親族、故人と親しい友人や同僚などと形見を分け合う日本の伝統的な風習です。
近年はもしものときに備える終活の一環として、生前のうちに身辺整理をして、自分自身で形見分けをするケースも増加傾向にあります。
形見分けの起源と歴史
形見分けの歴史は平安時代にまで遡るといわれており、当時の『栄華物語』には「あはれなる御形見の衣は」と、貴族の着物に関する形見分けについて記されています。
地域によっては「袖分け」「裾分け」などとも呼ばれていますが、かつての形見分けは、故人が袖を通した衣類を分け合うのが一般的でした。
時代の変化とともに、時計や万年筆など、維持しやすい品物を形見分けするようになりましたが、形見には故人の霊魂を受け継ぐという意味合いが込められています。
形見分けを行う理由と意義
形見分けを行うのには、次の3つの意義があります。
- 故人を偲んで生前の思いや価値観を共有できる
- 形見分けの品物を通じて故人の存在を身近に感じられる
- 故人の遺品整理に際して遺族の負担を軽減できる
形見分けをした品物を通じて故人を偲び、思いを馳せることは、死別による悲しみを癒やす効果があり、グリーフケアとしても役立ちます。
参考:グリーフケアとは?意味や必要かどうかの判断ポイントと6つの方法を解説
さらに、親から子へ、子から孫へと、代々にわたって形見を継承するケースもあります。
ご先祖様の想いを大切にする心は、ご供養にも通じるといえるでしょう。
形見分けに最適なタイミングと時期

形見分けは忌明け後に行うのが最適で、親族や故人の友人など、身近な参列者が集まりやすいため、四十九日法要の当日に形見分けするのがおすすめです。
| 宗教 | 葬儀後の儀式 |
| 仏教 | 四十九日法要 |
| 神道 | 五十日祭 |
| キリスト教 | 召天記念日/追悼ミサ |
忌明けの四十九日法要は仏教特有の儀式ですが、他の宗教にも相応する時期があります。
形見分けには事前の準備が必要となるため、あらかじめ確認して早めに対応しましょう。
もし忌明けのタイミングを逃してしまった場合は、一周忌や三回忌をはじめ、遺族の都合のよい時期に形見分けをしても構いません。
一方、遺族が遺品整理を急ぐ必要がある場合や、賃貸住宅の解約、自宅の売却などの予定がある場合には、葬儀後すぐに形見分けを行うこともあります。
死後すぐに形見分けを行いたい場合は、身内同士でトラブルにならないよう、相続人全員の同意を得ておくことが大切です。詳しくは後述の注意点をご参照ください。
形見分けに最適な品物

形見分けに最適なのは、次のような故人が所有していた品物が対象です。
- 高級品:ブランド品・アクセサリー・時計・毛皮・着物
- 故人の愛用品:衣類・本・文具
- 故人の趣味:絵画・CD・DVD・コレクション
- 思い出の品:アルバム・写真
- 実用品:家具・家電
一般的には、受け取る方にとって価値を感じられるものが喜ばれます。
相手の好みや価値観に迷う場合は、いくつか候補となる品物を用意し、直接選んでもらうのもよいでしょう。
形見分けのマナーと手順

形見分けにおいて、マナーを守ってスムーズに進めるための4つの手順について解説します。
- 遺品整理をして形見分けする品物を選定する
- 誰に何を形見分けするかを想定してメモを取る
- 形見分けの品物をクリーニングする
- 日程を決めて形見を手渡しする
①遺品整理をして形見分けする品物を選定する
形見分けでは、あらかじめ遺品整理をしながら品物を選んでおくことで、失敗や後悔を防ぎやすくなります。
遺品整理では、形見分けするもの以外に、貴重品、リサイクルするもの、廃棄するものと種類を分別し、置き場所を決めて整理するのがおすすめです。
遺品整理については、詳しい手順を当ページの最後に参考記事としてご紹介していますので、ぜひご覧ください。
②誰に何を形見分けするかを想定してメモを取る
形見分けする品物を洗い出したら、誰に何を渡すかを想定してメモを取っておくと、譲渡する相手への連絡から引き渡しまでスムーズに進められます。
喪主、夫・妻、長男・長女など、形見分けには誰が取り仕切るというルールがなく、基本的に相続人同士で穏便に話し合って決めるのがマナーです。
親の形見分けなどでトラブルにならないための注意点については、後述にて詳しく解説しますので、どうぞご参照ください。
③形見分けの品物をクリーニングする
形見分けの品は、できるだけきれいに汚れを落としましょう。洋服類はクリーニングに出す、洗濯やアイロンがけをするなどの気遣いも大切なマナーです。
気になるシミや汚れ、破損や使用感などがある場合は、形見分けの際に正直に伝えて確認してもらうことで、お互いに嫌な思いをせず、気持ちよく受け渡しができるでしょう。
④日程を決めて形見を手渡しする
形見分けは基本的に手渡しがマナーのため、四十九日法要などの法事の日に形見分けを行う際は、会食中やその前後のタイミングを見計らって声をかけるとよいでしょう。
手荷物になる形見を譲る場合や、衣類など複数の品物から選んでもらう場合は、改めて自宅に来ていただけるよう、日程を調整するのがおすすめです。
形見分のトラブルを防ぐ7つの注意点

形見分けで法律違反やトラブルを防ぐためには、次の7つの注意点に気をつけましょう。
- 形見分けする品物は故人の遺志を尊重して法定相続人全員で決める
- 形見の品物の売却は事前に買い取り価格を査定してよく話し合って検討する
- 誰に何を形見分けするかを記録に残しておく
- 形見分けの品物によっては贈与税や相続税が発生する場合がある
- 形見分けする品物によっては名義変更など手続きが必要な場合がある
- 形見分けは、基本的に目上の方には行わない
- 形見分けの品物は包装しない
①形見分けする品物は故人の遺志を尊重して法定相続人全員で決める
親の形見分けを兄弟姉妹で行う場合など、形見分けでは親族トラブルが起こりやすいことに注意して、故人の遺志を尊重して法定相続人全員で決定しましょう。
法定相続人とは、故人の配偶者や子どもをはじめ、直系尊属や兄弟姉妹などにあたります。
出典:相続人の範囲と法定相続分(国税庁)
故人の意向を確認するには、まず遺言書やエンディングノート、遺書などの存在を調べて、口頭による遺言の有無についても確認しておくと身内の揉め事を防ぎやすくなるでしょう。
②形見の品物の売却は事前に買い取り価格を査定してよく話し合って検討する
形見分けの品物の多くは、買取業者やリサイクルショップへ売却することも可能ですが、必ず事前に買い取り価格を査定し、相続人同士でよく話し合って検討しましょう。
遺品整理業者には、不用品の買い取りから住まいの特殊清掃や売却・賃貸管理までまとめて委託できるケースもあるため、地域にある信頼できる業者へ相談してみるのがおすすめです。
③誰に何を形見分けするかを記録に残しておく
形見分けでトラブルを防ぐためには、誰に何を形見分けするかを一時的なメモだけでなく、きちんと文書にして記録し、相続人同士で共有しておくことをおすすめします。
遺産相続で土地や建物などを相続する際は、相続人同士で話し合い、公的に認可される「遺産分割協議書」を作成することが一般的となっています。
参考:遺産分割協議書とは?作成の流れや手続きを解説(三菱UFJ銀行)
相続税が発生するかどうかにかかわらず、形見分けをする際にも文書化しておくことで親族トラブルを回避しやすくなります。
揉めごとになるのが心配な場合は、ぜひ用意しておきましょう。
④形見分けの品物によっては贈与税や相続税が発生する場合がある
現金・金券・有価証券・ゴルフ会員権などの財産のみならず、高価な貴金属・宝石・骨董品・絵画などを形見分けする際は、遺産相続の対象となる可能性があるためご注意ください。
生前の場合は贈与税、死後の場合は相続税が発生し、被相続人と相続人の関係や金額によって税率や控除額が異なります。
参考:相続税の税率(国税庁)
参考:贈与税の計算と税率(暦年課税)(国税庁)
なお、相続税には支払い期限があり、故人の死亡日(相続の開始があったことを知った日)の翌日から10か月以内に納付しなければならないため気をつけましょう。
⑤形見分けする品物によっては名義変更など手続きが必要な場合がある
形見分けでは、車やバイクは名義変更の手続きが必要となります。
また、パソコンやスマートフォンなどの端末は、アプリやサブスクリプションの解約、名義変更にご注意ください。
飼い主が亡くなった犬や猫などのペットの所有権は相続人となるため、マイクロチップの登録証明書を入手のうえ、所有者の登録情報の変更届が必要となることにも気をつけましょう。
なお、とくにペットなどは故人が生前のうちに「死後事務委任契約」を締結し、死後の引き継ぎ先を決めている場合もあるため、その際は契約相手の受任者へ連絡をしてください。
⑥形見分けは、基本的に目上の方には行わない
形見分けは、目上の方には行わないのがマナーとされているため、お世話になったからといって、恩師や上司に渡すのは基本的に避けましょう。
目上の方が形見分けを希望される場合は、「たいへん失礼ですが、お受け取りいただけますか?」と丁重に伺いましょう。
後輩に対しても無理に押し付けないのが、形見分けのマナーです。
⑦形見分けの品物は包装しない
形見分けは、高価な品物であってもラッピングをしないのがマナーです。
どうしても包装したい場合は、半紙やコピー用紙などの白い紙で簡易的に包みましょう。
アクセサリーなどの小物はチャック付きのポリ袋を使用したり、衣類は持ち帰り用としてショップバッグや紙袋などを用意してあげたりすると、気遣いや親切さが伝わるでしょう。
形見分けに関するよくある質問
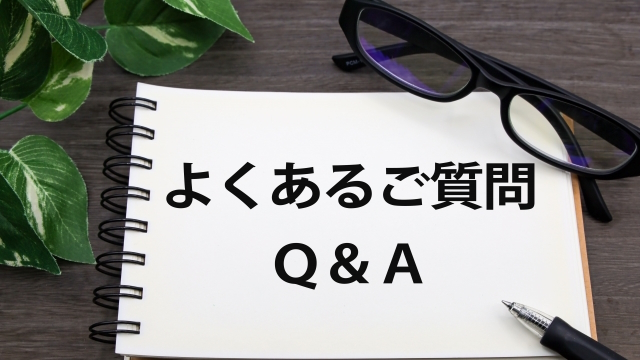
形見分けに関してよくある質問をご紹介しますので、気になる項目があればチェックしてください。
形見分けをしない方がよい品物は?
故人に異存がなく、受取人と相続人全員が合意していれば、基本的にどのようなものでも形見分けは可能ですが、一般的にはトラブルを避けるため、次のような品物は控えます。
- 相続税や贈与税の対象や特別に高価なもの
- 命のある生き物や責任負担がかかるもの
- 専門知識が必要なものや取り扱いが難しいもの
- 置き場所や保管に困るもの
近年はリサイクルという観点からラフな気持ちで形見分けするケースも増えていますが、該当する形見分けの品物にはくれぐれも注意して、故人の立場になって慎重に判断してください。
形見分けをもらった場合のお礼は?
形見分けはプレゼントとは違い、受け取った際に返礼品や礼状などのお礼を用意する必要はありません。
どうしても気になる場合は、仏花やお供え物を用意してお墓参りしたり、命日にお花を贈ったりと、故人の供養として形にするとよいでしょう。
形見分けを譲渡や廃棄処分する方法は?
形見分けの品物を他人に譲渡するのはマナー違反とされており、受け取った本人が故人に代わって大切にしていくのが望ましいとされています。
やむを得ず廃棄する場合は、個人情報に注意して適切に処分しましょう。
ゴミとして廃棄することが気になる場合は、読経供養をともなうお焚き上げを行うか、お清めの塩を撒いてから処分するとよいでしょう。
まとめ:形見分けは7つの注意点に気をつけて忌明け過ぎに行うのが基本マナー

形見分けの基礎知識と適切な時期や手順、気をつけるべき注意点などについて解説しましたが、まとめると次のとおりです。
- 形見分けは古くからの日本の風習で、故人の生前の思いや価値観を共有することで、遺族の喪失感を癒やし、遺品整理の負担軽減にも役立つ。
- 形見分けの時期は四十九日法要などの忌明け後に行うのが最適だが、タイミングを逃したら一周忌や遺族の都合のよい時期で問題なく、遺品整理などの事情で葬儀後すぐに行うケースもある。
- 形見分けに最適な品物は、ブランド品やアクセサリー・時計などの高級品や、故人の愛用品や趣味の品をはじめ、思い出の品や家具・家電などの実用品など、貰い手にとってメリットのあるものが選ばれる。
- マナーを守ってスムーズに形見分けをするにはコツがあり、次の4つのステップで進めるとよい。①遺品整理をして形見分けする品物を選定する ②誰に何を形見分けするかを想定してメモを取る ③形見分けの品物をクリーニングする ④日程を決めて形見分けを手渡しする
- 形見分けで法律違反やトラブルを防ぐには、次の7つの注意点に気をつける。①故人の遺志を尊重して法定相続人全員で決める ②売却する際は事前に買い取り価格を査定してよく話し合う ③誰に何を形見分けするかを記録に残す ④品物によっては贈与税や相続税が発生する場合がある ⑤名義変更など手続きが必要な場合がある ⑥基本的に目上の人には形見分けをしない ⑦包装しない
形見分けでは、思いがけないトラブルやハプニングが起こる可能性があるため、相続人同士の話し合いを重視して、後々まで揉め事にならないように配慮しましょう。
北のお葬式では、北海道一円で葬儀を承っており、葬儀後の遺品整理や不用品の処分・買取、遺産相続を伴う形見分けや不動産に関するご相談まで、幅広く対応しております。
「はじめての葬儀で、葬儀後のことまで考えていなかった」というお客様にも安心してご利用いただけるよう、専任スタッフがサポートいたしますので、葬儀前から葬儀後まで安心してご利用いただけます。






