家族や身近な方が亡くなり、訃報連絡や葬儀案内を行う際、電話やメールでどのように伝えればいいのか、よく分からない方もいらっしゃるでしょう。
訃報連絡では、訃報を伝える順序や言葉遣いなど、相手や故人の関係者へ失礼のないよう、気をつけなければならないマナーがあります。
本記事では「いつ」「誰に」「どのような手段で」「何を伝えるべきか」といったポイントを押さえて、訃報連絡の仕方や注意点を分かりやすく解説します。
メール・LINEで手軽に訃報連絡ができるよう、相手別やさまざまなケース別にコピペできるおすすめの例文もご紹介しますので、ぜひご利用ください。
目次
訃報連絡とは?

訃報連絡の意味や役割について解説しますので、訃報の連絡をする心得として、あらかじめ理解を深めておきましょう。
訃報連絡の意味
訃報とは、「ふほう」と読み、故人が亡くなった事実を親族や友人・知人などへ知らせるための連絡です。
訃報連絡では、死亡したことだけを伝える場合もありますが、同時に葬儀の日時や場所などの葬儀案内を行うケースもあります。
訃報連絡の役割と必要性
訃報連絡には、次の5つの重要な役割があるため、喪主や遺族などの訃報を連絡する方は、その必要性を知っておきましょう。
- 故人が亡くなった事実や葬儀に関する情報を迅速かつ正確に伝えられる
- 葬儀への参列を促したり参列者を制限することができる
- 相手の弔意に関して、故人や遺族の意向を伝えることができる
- 参列者にとってスムーズに葬儀の参列準備ができる
- 遺族の不幸と喪中期間に入ることを伝えられる
故人が亡くなった事実や葬儀に関する情報を迅速かつ正確に伝えられる
訃報連絡によって、故人や遺族の関係者に対して、死亡の事実や葬儀に関する詳細情報を迅速かつ正確に伝えることができます。
勤務先の企業によっては、従業員からの訃報連絡に基づき、人事部や総務部などから社内通知として訃報が配信されるケースなどもあります。
葬儀への参列を促したり参列者を制限することができる
訃報連絡では、葬儀への参列を促して会葬者を集めることや、あらかじめ決めた人以外の参列者を制限することができます。
お葬式には葬儀形式があり、特に家族葬や直葬といった葬儀形式を選択する際は、想定外の参列者が訪れないように、身内だけの葬儀であることを訃報連絡でしっかりと伝えましょう。
| 種類 | 人数目安 | 通夜 | 葬儀・告別式 | 火葬 | 特徴 |
| 一般葬 | 30名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 不特定多数の会葬者を招く |
| 家族葬 | 30名未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 少人数の参列者 |
| 一日葬 | 30名未満 | ✕ | 〇 | 〇 | 通夜を省略した家族葬 |
| 直葬・火葬式 | 数名 | ✕ | ✕ | 〇 | 基本的に火葬のみ |
相手の弔意に関して、故人や遺族の意向を伝えることができる
訃報連絡では、葬儀や相手の弔意に関して、故人や遺族の意向を伝えることができるため、故人との理想的なお別れの形を実現しやすくなります。
近年の家族葬では、香典・供花・弔電・供物などの弔意を辞退したり、自宅への弔問をお断りするケースが増えているため、希望があれば訃報連絡で事前に伝えましょう。
参列者にとってスムーズに葬儀の参列準備ができる
訃報連絡は、参列者にとってもメリットがあり、葬儀の日時のスケジュール調整や、喪服や香典などの参列の準備をスムーズに行うことができます。
近年は家族葬の増加により、参列者側にとって葬儀へ参列してよいのかどうか迷いやすくなっているため、訃報連絡による葬儀の案内はとても重要です。
かつては、誰でも参列できる一般葬が主流でしたが、最新の葬儀形式に関する調査によると、約7割が家族や親族のみなど、参列者が制限される小規模のお葬式となっています。
遺族の不幸と喪中期間に入ることを伝えられる
訃報連絡を行うことによって、遺族にとって不幸が起こり、喪中期間に入ることを伝えられます。
喪中とは、故人の一周忌を迎えるまでの1年間のことをいい、遺族は一般的におめでたい行事や派手な行動を避けて、慎ましく過ごす期間にあたります。
訃報連絡をしておくことで、自分自身の心情や置かれた立場を周囲に察してもらえるため、先々が過ごしやすくなるでしょう。
訃報連絡をするタイミングと相手の優先順位

訃報連絡をする際は、3つのタイミングがあり、相手によって優先順位もあるため、適切な組み合わせについて解説します。
| タイミング | 相手 |
| 亡くなったらすぐ |
|
| 葬儀の日程が決まったらすぐ |
|
| 葬儀が終わってから |
|
亡くなったらすぐに訃報連絡
亡くなったらすぐ、家族や故人と血縁関係にあたる親族を筆頭に、次の順序で訃報連絡を行いましょう。
家族→故人の親・子供・兄弟姉妹→その他の故人や配偶者の親族→特に故人と親しかった友人→故人の勤務先や介護施設など
病院や警察で死亡が確認されたら、葬儀社へ依頼をしてご自宅や斎場へご遺体を安置し、葬儀プランや日程に関する打合せを行うのが一般的な死後の流れです。
葬儀の日程は、葬儀社を介して斎場や火葬場の空き状況を調べたうえ、お付き合いのある菩提寺の都合を確認する必要があります。
お付き合いをしている寺院がない場合は、葬儀社へ依頼をして僧侶を手配することも可能なため、喪主は遺族と話し合って速やかに方針を決定しましょう。
葬儀の日程が決まったらすぐに訃報連絡
葬儀の日程が決まったら、近親者や葬儀へ参列してもらう方をはじめ、次の優先順序で葬儀に関する詳細情報を伝えましょう。
すでに訃報連絡をした方→故人の友人・知人→葬儀へ招く遺族の関係者→遺族の親しい友人・知人→遺族の勤務先や学校→近隣住民・町内会・自治会など
上記のほか、故人が生前交流していた方や加入している団体など、日常でお付き合いのあった方へ訃報連絡を行います。
故人の訃報の連絡先を調べるには、次のような現物から調べるのが一般的ですが、故人の友人・知人へ聞き取りするのもおすすめです。
- エンディングノート
- 携帯電話・パソコンの連絡先
- 電話帳
- 年賀状や手紙・はがき
遺族は、勤務先や学校への訃報連絡とともに、忌引き休暇の申請も忘れないようにしましょう。
訃報連絡は、新聞のお悔やみ欄を利用して行う方法もあり、著名人のほか、北海道など地域によっては一般の方が亡くなった際、葬儀社へ依頼すると掲載ができます。
葬儀が終わってから訃報連絡
訃報連絡は、必ずしも葬儀前に行う必要はありません。身内のみの家族葬や直葬では、次のような方へ葬儀が終わってから報告することが多い傾向にあります。
- 葬儀へ招かない方
- 日常でお付き合いをしていない知人
葬儀後の訃報連絡は、『喪中はがき(年賀欠礼状)』が便利で、年賀欠礼の挨拶はメールやLINEでも送れます。時期や文面については、文例を掲載していますので、ぜひご覧ください。
ただし、人づてに訃報を聞いて、葬儀への参列や香典などをくださった方へは、葬儀後の挨拶廻りやお礼状により、しっかりと挨拶をしましょう。
訃報連絡の方法

| 手段 | 迅速 | 正確 | 社会性 |
| 電話 | 〇 | ‐ | 〇 |
| メール | ‐ | 〇 | 〇 |
| LINE | △ | △ | △ |
訃報連絡をする方法は、基本的に「電話」「メール」「LINE」の3つがあり、状況と相手によって手段を選択するのが一般的です。
社葬により企業から取引先などへ訃報連絡をする場合は、FAXを用いる場合や、封書やはがきを郵送するケースなどもあります。
電話
電話は、最も早く直接相手に情報を伝える手段として最適で、故人の死亡時や遺族の急な欠勤・欠席など、緊急性の高いケースの連絡に適しています。
ただし、相手が電話に出ない場合なども考えられるため、留守番電話の場合は録音し、改めて電話をかけるといった配慮も必要です。
メール
メールは、最も正確に情報を伝える手段として適しており、葬儀の日時や場所などの詳細を伝える場合に最適です。
社会的な位置付けとして、勤務先や取引先などの相手にも失礼がなく、電話とは違い、伝えたいことをしっかりとチェックして発信できるメリットもあります。
しかし、相手がいつメールを確認するかどうかが分からず、すぐに開封できないケースなどもあるため注意が必要です。
LINE
LINEは手軽なため、電話が繋がらない場合や、家族や親族、友人・知人などの親しい関係にある方に対してなら、訃報連絡や葬儀案内に利用しても問題ありません。
ただし、職場の上司など、目上の相手への訃報連絡は失礼になる可能性があり、スタンプや絵文字などはマナー違反にあたるため、避ける配慮が必要です。
LINE以外のSNSにおいても基本的なマナーは同様ですが、訃報連絡では第三者の目に触れてトラブルに巻き込まれないようにご注意ください。
訃報連絡の最適な手段の選び方の2つのポイント
訃報連絡の方法について、最適な手段の選び方にはコツがあるため、知っておくべき2つのポイントについて解説します。
- 訃報連絡で最も大切なことは『迅速さ』と『正確さ』
- 訃報連絡を『確実』に伝えるには2つの手段を用いるとよい
訃報連絡で最も大切なことは『迅速さ』と『正確さ』
亡くなったらすぐに行う訃報連絡では、何よりも迅速さが重要なため、家族や親族、故人と特に親しい方へは、まず電話で相手に連絡するのがおすすめです。
一方で、葬儀の日時や場所などの詳細情報については、聞き間違いや勘違いがないよう、記録に残るメールやLINEなどの文章として送信した方が助かる相手も多いでしょう。
訃報連絡を『確実』に伝えるには2つの手段を用いるとよい
訃報連絡を確実に相手に伝えるためには、電話とメール(LINE)を組み合わせると安心です。
葬儀案内においても、「メール(LINE)をお送りしましたのでご確認ください」と、電話で連絡するようにしましょう。
訃報連絡のマナーと7つの注意点

訃報連絡ではマナーがあるため、気をつけるべき7つの注意点について解説します。
- 連絡先リストを用意して速やかに連絡をする
- 名乗る際は故人との続柄や関係性を伝える
- 訃報や葬儀の情報は要点を箇条書きで伝える
- 連絡する時間帯に注意する
- 忌み言葉を避ける
- 句読点を省略する
- 葬儀における意向は明確に伝える
①連絡先リストを用意して速やかに連絡をする
訃報の連絡をする際は、速やかに知らせることが大切なため、あらかじめ連絡先リストを用意して、家族で手分けをして連絡するのがおすすめです。
連絡先はリスト化しておくことによって、相手とコンタクトが取れた場合や、参列の可否をチェックする際にも役立ちます。
②名乗る際は故人との続柄や関係性を伝える
普段あまり連絡を取らない親族や故人の関係者へ電話やメールで連絡をする際は、自分が誰なのかがすぐ分かるように、最初の名乗りでは、故人との続柄や関係性を伝えましょう。
特に高齢の方に対しては、故人が勤務していた社名や、縁のある地域名など、相手にとって故人が誰なのかが分かりやすいように伝える配慮も大切です。
③訃報や葬儀の情報は要点を箇条書きで伝える
訃報や葬儀の情報は要点を箇条書きでまとめて伝えることで、相手にとって必要な事項を把握しやすくなります。
- 故人の氏名
- 自分の名前・続柄
- 亡くなった日時
- 死因(任意)
- 葬儀の日程・場所
- 葬儀社名・連絡先
- 宗教・宗派
- 喪主の名前・連絡先
- 家族葬や一日葬など特徴のある葬儀形式の場合はその旨を記載
- 家族や親族へは集合時間を明記する
家族や親族へ葬儀の案内をする際は、一般参列者よりも1〜2時間程度早く斎場へ集合する必要があるため、掲載する時間を変更するか、注意事項として追記しましょう。
④連絡する時間帯に注意する
家族以外に訃報連絡をする際は、時間帯に注意し、深夜や早朝を避けて、朝8時〜夜22時頃までを目安に連絡するようにしましょう。
危篤の場合、故人の血縁者へは時間を問わず連絡するケースも多くありますが、訃報連絡は日中に行うのが基本マナーです。
メールやLINEによる訃報連絡では、時間指定による予約配信もできるため、利用する際はきちんと連絡できているかどうかまで、しっかりとチェックしましょう。
⑤忌み言葉を避ける
訃報連絡や葬儀では、避けなければならない『忌み言葉(いみことば)』と呼ばれる言葉遣いがあるため、使わないように注意しましょう。
- 死や別れを表す言葉:「死ぬ」「急死」「生きる」など
- 不幸が重なることを連想させる言葉:「重ね重ね」「度々」「再び」「次々」など
- 縁起の悪い数字:「4(死)」「9(苦)」
⑥句読点を省略する
訃報連絡では、葬儀が滞りなく終わるようにという願いを込めて、「、」「。」といった句読点を省略するのが正しいマナーです。
相手にとって読みやすいように、文章の区切りでは、改行やスペースを用いて表現しましょう。
⑦葬儀における意向は明確に伝える
葬儀に関して次のような要望があれば、参列者が理解を深められるように、葬儀の案内文へ明記して意向を伝えましょう。
- 参列者の人数の把握
- 香典・供花・弔電・供物・弔問などの辞退
- 故人の思い出の品や副葬品の収集
家族葬では、事前に参列者の人数を把握しておく必要があります。その場合は、参列の可否について返信をしてもらえるように、案内文でしっかりと依頼しましょう。
また、香典などを辞退したい場合は、具体的な名目を記載して、相手が戸惑ったり、突然の弔問に困ったりしないように対策を取りましょう。。
故人に関する思い出の品を持ち寄って語り合ったり、棺へ納める副葬品を収集したい場合など、葬儀に関するお願い事があれば、案内文で協力を求めても問題ありません。
相手別の訃報連絡の文例集【コピペ可】
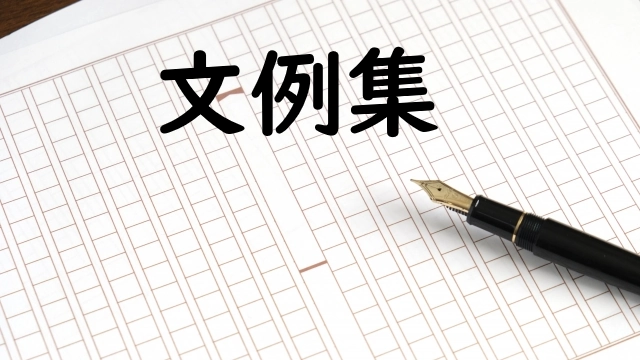
メールやLINEで簡単にコピペできる相手別の訃報連絡について、厳選した例文を文例集としてご紹介しますので、どうぞお気軽にご利用ください。
親族への訃報連絡の例文
親族に対して、電話やメール・LINEで訃報連絡や葬儀案内をする際の例文についてご紹介します。
親族へ電話で訃報を伝える場合
突然のご連絡失礼します。
〇〇の長男、〇〇です。
先ほど父が息を引き取りましたので、
取り急ぎご連絡いたしました。
葬儀については、改めてご連絡いたします。
遺体は〇〇にある斎場へ安置していますので、
もし対面をご希望の場合は、
私の携帯番号までご連絡ください。
携帯番号は000-000-0000です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
親族へメール・LINEで訃報を伝える場合
件名:訃報のご連絡/〇〇〇〇です
〇〇 〇〇様・ご家族様
突然のご連絡失礼いたします
〇〇 〇〇の長男 〇〇です
かねてより闘病しておりました父が
〇月〇日に〇歳にて永眠いたしました
生前のご厚誼に深謝し
心より御礼申し上げます
誠にありがとうございました
葬儀については詳細が決まり次第
改めてご連絡申し上げます
どうぞよろしくお願い申し上げます
〇〇 〇〇
連絡先:000-000-0000
親族へメール・LINEで葬儀案内を送る場合
件名:葬儀のご案内/〇〇〇〇より
〇〇 〇〇様・ご家族様
昨日はお電話にて失礼いたしました
〇〇 〇〇です
故・〇〇 〇〇の葬儀につきまして
下記のとおり家族葬にて執り行いますので
ご案内申し上げます
1.日時
通夜式:〇年〇月〇日 〇時〜(開式〇時)
告別式:〇年〇月〇日 〇時〜(開式〇時)
2.会場
〇〇斎場
住所:〇〇県〇〇市〇〇0-0-0
https:XXXXX.com
3.葬儀社
〇〇葬儀社
電話番号:000‐000-0000
4.宗教形式
浄土真宗 本願寺派
5.喪主
〇〇 〇〇(長男)
電話番号:000-000-0000
故人の遺志により香典・供花などのご芳情は
固く辞退申し上げますので
ご容赦賜りますようよろしくお願い申し上げます
ご多用中のところ申し訳ございませんが
参列の可否についてご返信をいただきたく
どうぞよろしくお願い申し上げます
〇〇 〇〇
連絡先:000-000-0000
故人の友人・知人への訃報連絡の例文
故人の友人・知人に対して、電話やメール・LINEで訃報連絡や葬儀案内をする際の例文についてご紹介します。
故人の友人・知人へ電話で訃報を伝える場合
突然のご連絡失礼いたします。
私、〇〇様がお勤めの〇〇会社に勤務していた
〇〇〇〇の息子、長男の〇〇〇〇と申します。
昨日、父の体調が急変し、
そのまま息を引き取りました。
〇〇様のおかげで父は幸せだったと思います。
退職後も父を温かく見守っていただき、
本当にどうもありがとうございました。
厚かましいお願いばかりで恐縮なのですが、
葬儀は家族葬にしたいと考えており、
ぜひ、〇〇様にもご参列いただければと存じます。
詳細が決まり次第、ご連絡いたしますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
何かございましたら、こちらの携帯番号まで
お気軽にご連絡くださいませ。
それでは、どうぞよろしくお願い申し上げます。
故人の友人・知人へメール・LINEで訃報連絡と葬儀案内をする場合
件名:葬儀のご案内/〇〇〇〇です
〇〇 〇〇様
突然のご連絡失礼いたします
〇〇 〇〇の長男 〇〇と申します
かねてより闘病しておりました父が
〇年〇月〇日 〇歳にて永眠いたしました
故人への生前のご厚誼を深く感謝いたします
誠にありがとうございました
つきましては 葬儀について
下記のとおりご案内申し上げます
1.日時
通夜式:〇年〇月〇日 開式〇時〜
告別式:〇年〇月〇日 開式〇時〜
2.会場
〇〇斎場
住所:〇〇県〇〇市〇〇0-0-0
https:XXXXX.com
3.葬儀社
〇〇葬儀社
電話番号:000‐000-0000
4.宗教形式
仏式(浄土宗)
喪主:〇〇 〇〇
連絡先:000-000-0000
故人の勤務先への訃報連絡の例文
故人の勤務先に対して、電話やメール・LINEで訃報連絡や葬儀案内をする際の例文についてご紹介します。
故人の勤務先へ電話で訃報を伝える場合
(※電話は所属長へ繋いでもらいましょう)
お忙しいところ失礼いたします。
〇〇部〇〇課の〇〇の妻、〇〇と申します。
急用がありお電話させていただきました。
恐れ入りますが、〇〇部〇〇課の
上長様はいらっしゃいますでしょうか。
(※所属長から総務部などへ伝える流れです)
お忙しいところ失礼いたします。
〇〇の妻、〇〇〇〇と申します。
いつもお世話になっております。
本日、早朝に主人が息を引き取りましたので、
取り急ぎご連絡申し上げました。
生前はご心配とご迷惑をおかけして
誠に申し訳ございません。
ご理解いただき、ありがとうございました。
葬儀につきましては、詳細が決まり次第、
メールでご案内させていただきたいのですが、
お名前の漢字とメールアドレスを
ご教示いただけますでしょうか。
(※相手の連絡先は必ず復唱して確認する)
それでは、追ってご連絡申し上げます。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、
部署の皆様へもどうぞよろしくお伝えください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
故人の勤務先へメールで葬儀案内をする場合
件名:葬儀のご案内/〇〇〇〇です
株式会社〇〇〇〇 〇〇部
部長 〇〇 〇〇様
先日はお電話にて失礼いたしました
夫 〇〇 〇〇が〇月〇日 永眠いたしましたので
通夜・告別式につきまして
下記のとおりご案内申し上げます
1.日時
通夜式:〇年〇月〇日 開式〇時〜
告別式:〇年〇月〇日 開式〇時〜
2.会場
〇〇斎場
住所:〇〇県〇〇市〇〇0-0-0
https:XXXXX.com
3.葬儀社
〇〇葬儀社
電話番号:000‐000-0000
4.宗教形式
仏式(曹洞宗)
ご不明な点などございましたら
以下の私の携帯電話までご連絡ください
どうぞよろしくお願い申し上げます
喪主:〇〇 〇〇
連絡先:000-000-0000
友人・知人への訃報連絡の例文
遺族の友人・知人へ電話やメール・LINEで訃報連絡や葬儀案内をする際の例文についてご紹介します。
友人・知人へ電話で訃報を伝える場合
突然のお電話ですみません。
〇〇です。
昨晩、主人が他界いたしましたので、
取り急ぎご連絡申し上げます。
しばらくサークル活動への参加を
欠席させていただきますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
葬儀につきましては、故人の遺志に基づいて
身内のみで家族葬を執り行います。
お香典・ご弔電・ご供花・ご弔問に関しては
辞退させていただきますので、
たいへん申し訳ございませんが、
皆様へもどうぞよろしくお伝えください。
急なお電話を失礼いたしました。
友人・知人へメール・LINEで訃報連絡と葬儀案内をする場合
件名:〇〇〇〇です/訃報のご連絡
〇〇 〇〇様
突然のご連絡失礼いたします
闘病中だった夫 〇〇 〇〇が
〇年〇月〇日 〇歳で永眠いたしました
生前のご厚情に深く感謝申し上げます
葬儀につきましては近親者のみで執り行います
御香典・御弔電・御供物・御弔問については
固く辞退申し上げますので
ご配慮いただきますようお願い申し上げます
喪主:〇〇〇〇
追伸
落ち着いたらご連絡いたします
どうぞ心配なさらずにお過ごしください
近所の方や町内会への訃報連絡の例文
近所の方や町内会などに対して、電話やメール・LINEで訃報連絡や葬儀案内をする際の例文についてご紹介します。
近所の方や町内会へ電話で訃報を伝える場合
突然のご連絡失礼いたします。
〇〇に住んでおります〇〇です。
昨日、入院しておりました主人が永眠いたしましたので、
ご連絡申し上げます。
生前は多々お心遣いいただきまして
誠にありがとうございました。
葬儀は自宅にて執り行う予定でございます。
もしよろしければ町内の皆様に
ご支援いただけると助かります。
詳細が決まりましたら、
改めてご連絡いたしますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
お手数をおかけして申し訳ございませんが
皆様へもよろしくお伝えくださいませ。
近所の方や町内会へメールで葬儀案内をする場合
件名:〇〇〇〇です/葬儀のご案内
町内会長 〇〇様
先日は突然のお電話を失礼いたしました
夫 〇〇 〇〇が〇月〇日 永眠いたしましたので
通夜・告別式について下記のとおり
ご案内申し上げます
1.日時
通夜式:〇年〇月〇日 開式〇時〜
告別式:〇年〇月〇日 開式〇時〜
2.会場
〇〇宅(自宅)
住所:〇〇県〇〇市〇〇0-0-0
3.葬儀社
〇〇葬儀社
電話番号:000‐000-0000
4.宗教形式
仏式(真宗大谷派)
この度はお力添えを賜りまして心より御礼申し上げます
お手伝いをお願いしております皆様には
開式の1時間前を目安にお集まりいただけますと幸いです
何かございましたらお気軽にご連絡ください
どうぞよろしくお願い申し上げます
喪主:〇〇 〇〇
連絡先:000-000-0000
ケース別の訃報連絡の文例集

さまざまなケース別の訃報連絡におけるメールやLINEの例文をご紹介しますので、相手や状況に合わせて、どうぞご活用ください。
家族葬の訃報連絡における例文
家族葬で要望がある際は、参列者の理解を得られるように、あらかじめ訃報や葬儀の連絡で伝えましょう。
一日葬でお通夜をしない場合の例文
夫 〇〇 〇〇が〇月〇日 永眠いたしました
葬儀は故人の遺志に基づき
身内のみで一日葬を執り行います
通夜式を省略いたしますので
何卒ご容赦ください
略喪服で家族葬を行う場合の例文
妻 〇〇 〇〇が〇月〇日 永眠いたしましたので
葬儀は家族葬にて執り行います
故人の遺志に基づき 明るく和やかな雰囲気で
最後のお別れをしたいと思いますので
当日は平服でお越しください
参列者の人数を把握したい場合の例文
父 〇〇 〇〇が〇月〇日 永眠いたしましたので
葬儀につきましては 故人の遺志を尊重し
以下のとおり家族葬にて執り行います
お手数ですが ご出席の可否について
ご返信いただけますと幸いです
無宗教葬儀の訃報連絡における例文
無宗教葬儀で参列者へのお願い事がある場合は、あらかじめ訃報や葬儀の連絡で依頼しておきましょう。
故人の思い出の品物や写真などを収集したい場合の例文
故 〇〇 〇〇が〇月〇日 永眠いたしました
葬儀につきましては 故人の遺志を尊重し
以下のとおり無宗教にて執り行います
つきましては 故人との思い出を語らいながら
最後のお別れをさせていただきたく
写真などのお品をお持ちいただければ幸いです
注意事項を伝える葬儀案内の例文
式場に関して注意事項がある場合は、あらかじめ葬儀案内の式場に関する項目欄で伝えて、トラブル対策を行いましょう。
駐車場が少ない場合の例文
斎場の駐車場に台数制限がございますため
公共交通機関やタクシーにてお越しください
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます
交通アクセスが分かりにくい場合の例文
最寄り駅からの交通アクセスや
斎場周辺の地図につきましては
以下のホームページをご参照ください
宿泊施設の予約の必要性を確認する場合の例文
宿泊施設の予約が必要な場合は当方にて
斎場または周辺のホテルを予約いたしますので
ご連絡いただきますようお願いいたします
高齢者・妊婦など特定の方へ配慮した訃報連絡の例文
(※文末へ追記しましょう)
追伸:ご参列は無理なさらずにご自愛ください
追伸:ご参列いただける際はご一報くだされば家族が迎えに参ります
葬儀の事後報告の例文
件名:〇〇 〇〇 訃報のご連絡/〇〇 〇〇
〇〇 〇〇様
突然のご連絡失礼します
長女の〇〇 〇〇です。
かねてより療養中の母 〇〇 〇〇が
令和〇年〇月〇日に永眠いたしました
生前のご厚情に深く感謝申し上げます
葬儀は近親者のみで執り行いました
事後のご通知となりましたこと
何卒ご容赦ください
ここに謹んでご通知申し上げます
〇〇 〇〇
住所:〇〇県〇〇市〇〇0-0-0
連絡先:000-000-0000
年賀欠礼文(喪中はがき相当)の例文
〇〇 〇〇様
喪中につき年末年始のご挨拶を謹んでご遠慮申し上げます
本年〇月〇日に父 〇〇 〇〇が永眠いたしました
本年中の御厚情に深謝いたしますとともに
明年も変わらぬ御厚誼のほど
どうぞお願い申し上げます
〇〇 〇〇
住所:〇〇県〇〇市〇〇0-0-0
連絡先:000-000-0000
訃報連絡に関してよくある質問
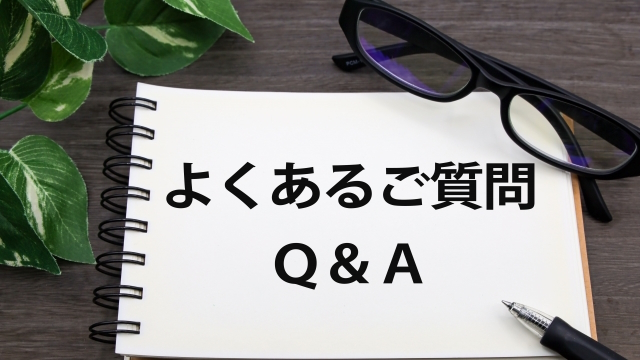
訃報連絡に関して、よくある質問をご紹介しますので、気になる項目があれば事前にチェックして、不明点やお悩みの解消にお役立てください。
家族葬で訃報連絡を送る場合の範囲はどこまで?
家族葬で訃報連絡をして葬儀へ参列するのは、一般的に故人から見て三親等までとするケースが多いものの、四親等のいとこ、甥・姪が参列する場合も多くあります。
家族葬では、参列してほしい人には事前に連絡して、葬儀に招かない人には事後報告が一般的です。
ただし、関係性によっては臨機応変な対応が必要となります。
事前に連絡する際は、「身内のみで葬儀を営みます」などと明記して、葬儀に関する内容を省略して、生前にお世話になったことへのお礼を伝えましょう。
喪中はがきはいつからいつまでに送るの?
喪中であることを伝える喪中はがき(年賀欠礼はがき)は、11月中旬から遅くとも12月初旬までに発送しましょう。
早いと受取人が喪中であることを忘れたり、遅いと年賀状を準備してしまったりするため、送る時期には注意が必要です。
喪中はがきを送付していない方から年賀状が届いた場合は、「寒中見舞い」によって、松の内が明けた1月8日から2月4日頃の立春までに到着するように送ります。
立春を過ぎた場合は、「余寒見舞い」という言葉を用いることで、2月末頃までの幅広い時期に対応可能です。
訃報連絡が届いたらどうするの?
訃報連絡が届いたら、まず「お悔やみ申し上げます」「ご愁傷様でございます」と、お悔やみの言葉を伝えるのがマナーです。
メールやLINEで訃報連絡が届いた場合は、同じようにメールやLINEで返信しても失礼にあらたらないため、以下の文例集を参考に適切なお悔やみの言葉を送りましょう。
参考:お悔やみメールの例文20選!コピペで使える相手やシーン別の文例集
まとめ:訃報連絡の例文はコピペが簡単で便利!相手やケースに合わせて葬儀案内をしましょう

訃報連絡のマナーや注意点について解説し、厳選した相手別と電話・メールなどの手段の例文やシーンに合わせた文例をご紹介しましたが、まとめると次のとおりです。
- 訃報連絡には、故人が亡くなった事実や葬儀に関する情報を迅速かつ正確に伝え、理想の葬儀を実現しやすくしたり、参列者の準備を促す役割がある。
- 訃報連絡には、亡くなってすぐ・葬儀の日程が決まったらすぐ・葬儀後と、3つのタイミングがある。家族や故人と血縁関係にある親族から順に、電話・メール・LINEで連絡をするが、訃報は電話、葬儀案内はメールや電話など、2つの手段を用いると迅速かつ正確に伝えられる。
- 訃報連絡では次の7つの注意点に気をつける。①連絡先リストを用意して速やかに連絡する ②名乗る際は故人との続柄や関係性を伝える ③訃報や葬儀の情報は要点を箇条書きで伝える ④連絡する時間帯に注意する ⑤忌み言葉を避ける ⑥句読点を省略する ⑦葬儀における意向は明確に伝える
訃報連絡は、エンディングノートなどから故人の関係者や葬儀に関する希望を汲み取り、家族で連携してスピーディーに行うことが大切です。
北のお葬式では、北海道のお葬式を承っております。ご葬儀の際は訃報連絡についてのご相談も承りますので、葬儀に関するご不安やご心配を感じられている方は、どうぞお気軽にお問合せください。
参考記事






